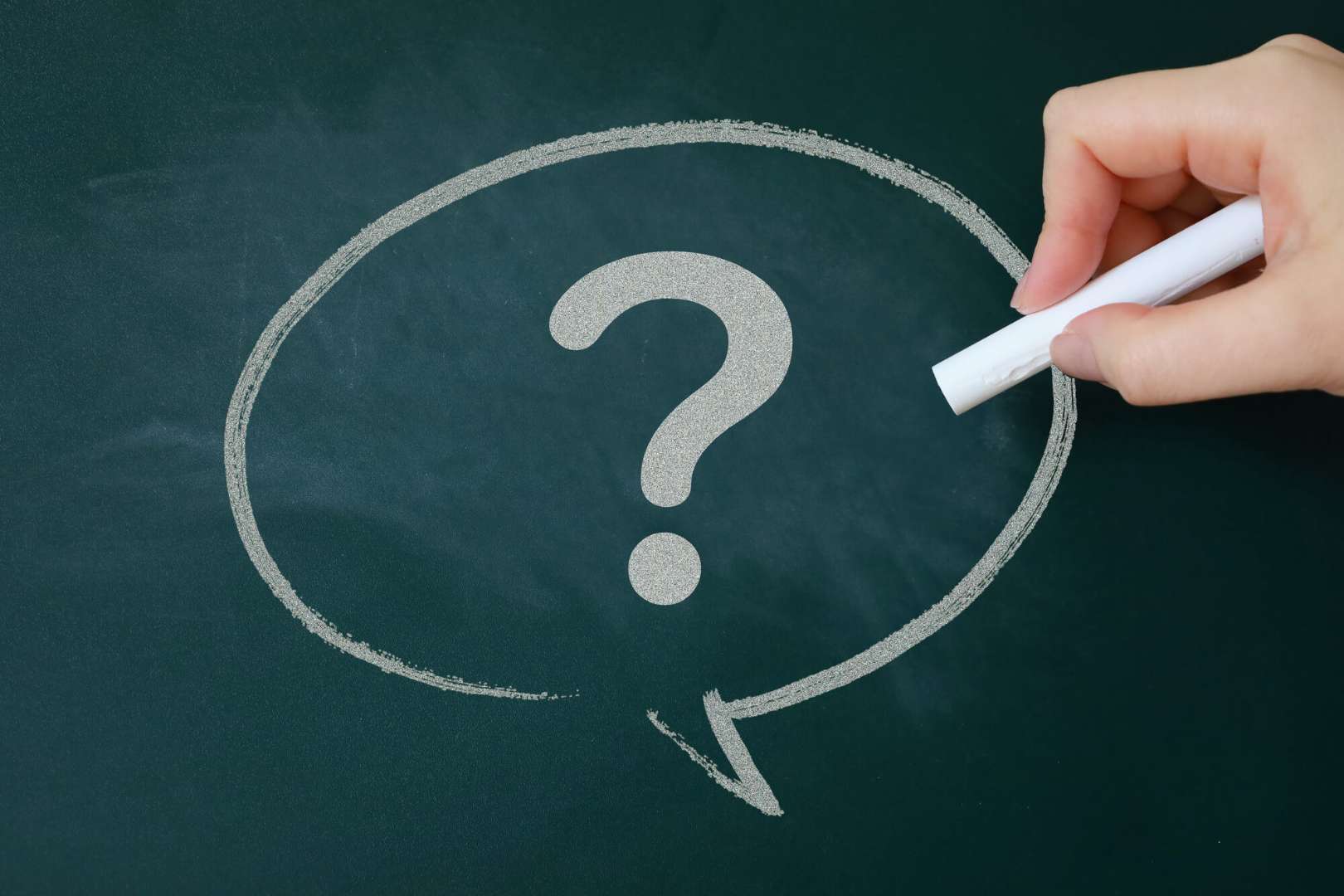「塗装工はきついわりに稼げない」といった印象を持たれている方は少なくありません。確かに、重労働や天候に左右される面があるため、収入面でも不安を感じやすい職種です。しかし実際には、現場経験や働く環境によって年収には大きな差があり、一律に「低い」とは言い切れません。
たとえば、地域や会社の規模、公共工事の割合などによっても給与水準は異なります。さらに、資格の有無や役職、職長としての責任を担うかどうかでも収入に差が出ます。中には、年収500万円以上を安定的に得ている職人もいます。
この記事では、「塗装工の年収は本当に安いのか?」という素朴な疑問に向き合いながら、収入の実態や伸ばし方、職場選びのポイントまで、現場目線で丁寧に掘り下げていきます。これから塗装業界を目指す方にとって、納得のいく判断材料となるよう、現実に即した視点でお届けします。
平均年収は350〜450万円?塗装業界の収入水準を具体的に解説
塗装工の平均年収は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査などをもとに見ると、全国的にはおおよそ350〜450万円の範囲に収まります。これはあくまで全体平均であり、勤続年数や職種、地域によってもばらつきがあります。特に、都市部では物価や人件費の関係から給与水準がやや高くなる傾向があります。
たとえば、未経験から見習いとしてスタートした場合、年収は300万円前後となることが一般的です。一方で、現場をまとめる職長クラスや、資格を持ち現場管理も担う人材であれば、年収500万円以上も十分に狙えます。また、手当や残業代、賞与の有無によっても実質的な手取り額は大きく異なります。
雇用形態も収入に影響します。正社員として安定した給与を得るケースもあれば、日給制や請負契約で働く職人もおり、後者の場合は繁忙期に大きく稼げる一方、仕事が少ない時期は収入が落ち込むリスクも伴います。安定を求めるのであれば、通年で現場がある企業に勤めるのが一つの方法です。
また、公共工事を多く請け負う会社では、業績が比較的安定しているため、社員の給与や賞与も一定水準が確保されやすい傾向があります。こうした点を踏まえて、求人情報を見る際は「月収」や「日給」の数字だけでなく、賞与実績や年間休日数、固定残業の有無など、総合的に判断することが大切です。
年収500万円超えも可能?収入を伸ばす人の特徴と行動パターン
塗装工として年収を上げていくには、ただ年数を重ねるだけでは足りません。実際に年収500万円以上を安定して稼いでいる人たちには、いくつか共通する特徴があります。ひとつは「現場全体を見渡す視点を持っていること」。作業だけでなく、安全や進捗管理も任されるようになると、それに応じた責任と報酬が伴います。
次に、資格の取得を積極的に行っていることも重要な要素です。たとえば「一級塗装技能士」や「有機溶剤作業主任者」などの資格は、会社からの信頼にもつながり、役職手当や資格手当として収入面に反映されやすくなります。加えて、元請けからの案件や公共工事での実績がある現場では、資格保持者が優先的に配置されることもあります。
また、仕事の正確さやスピード、コミュニケーション能力も重要です。塗装作業は単独ではなく、足場屋や左官など他業種との連携が欠かせません。チームで動く現場では、信頼される職人ほどリーダー的な立場を任されやすくなり、その分だけ給与にも反映されるのです。
現場での信頼を積み重ね、資格を取り、責任ある立場に進む——このようなステップを着実に踏むことで、塗装工としての収入は大きく伸ばすことができます。ただし、その道は短期間で手に入るものではなく、数年単位での努力と継続が前提です。収入を伸ばすには、将来を見据えた地道な積み重ねが不可欠だと言えるでしょう。
同じ職種でも年収に差が?会社選び・地域性の重要性
塗装工という職種において、仕事内容は似ていても、働く地域や所属する会社によって年収には明確な差が出ます。これは、単に「給与の高い会社を選べばよい」という話ではなく、業務の内容や施工体制、受注先の性質が影響しているためです。
たとえば都市部では、建築需要が高く案件の単価も上がるため、忙しい分だけ収入に反映されやすい傾向があります。一方で、地方では物価や人件費の水準が低く、年収はやや抑えめになることもあります。ただし、地方には地場の元請け企業と長く付き合っている塗装会社も多く、安定して仕事を得られるという強みもあります。
また、下請け中心の会社と、元請けや公共工事を手がける会社とでは、収入の安定性に差が出ます。下請けの場合、元請けの都合で仕事量が増減することもありますが、元請けに近い立場で工事を請け負う企業では、スケジュールや予算を自社で管理できる分、給与体系も整っている傾向があります。
福利厚生の有無や、賞与の支給実績、残業代の計算方法なども見逃せません。同じ「月収25万円」と書かれていても、年間休日が少なかったり、賞与がなかったりする場合、実質的な年収は大きく下がってしまいます。求人を見る際は、こうした条件面まで丁寧にチェックすることが欠かせません。
職人としての技術に自信がある人ほど、選ぶ環境によって得られる対価も変わってきます。だからこそ、どこで・誰と・どう働くかという視点が、年収を大きく左右するのです。
スタートは年収300万円台でも、どう成長できるか?
塗装工として働き始めたばかりの頃は、年収300万円台からのスタートになるケースが一般的です。特に未経験の場合は、最初の1〜2年は仕事を覚える期間として位置づけられ、給与よりも技術習得が優先される傾向があります。しかし、そこからどう成長するかによって、将来的な年収は大きく変わってきます。
まず重要なのは、ただ現場に出るだけでなく、「どんな作業を任されているか」「誰に評価されているか」を意識することです。言われた作業をこなすだけでなく、段取りや道具の準備、安全配慮まで含めて自発的に動ける人は、周囲から信頼され、早い段階で責任ある役割を任されるようになります。
次のステップとして有効なのが、資格取得です。「塗装技能士(二級・一級)」や「有機溶剤作業主任者」などの資格は、現場での扱いやすさだけでなく、手当や昇格にも直結します。資格を持つことで仕事の幅が広がり、他の職人との差別化にもつながります。
さらに、職長や現場リーダーといったポジションを目指すことで、年収は確実に上がっていきます。ここでは技術だけでなく、周囲との連携や段取り力、後輩の指導力など、総合的な現場力が求められます。決して簡単な道ではありませんが、目の前の仕事に真摯に取り組み、ひとつひとつ積み重ねていくことで、着実に評価されるようになります。
職場選びも見逃せないポイントです。技術の習得を支援してくれる環境や、資格取得を後押しする制度があるかどうかは、成長スピードに直結します。こうした環境を選べば、未経験からでも数年後には年収400万〜500万円台を目指すことも現実的です。
▶ 求人情報や職場の雰囲気が気になる方は、以下をご覧ください
https://www.mitsuwa-painting.com/recruit
塗装工の収入は「成長と選び方」で大きく変わる。自分に合った環境を探そう
塗装工という職種は、肉体労働というイメージだけで評価されがちですが、実際には技術や責任、経験が年収に直結する専門職です。スタート時は決して高収入とは言えなくても、継続してスキルを磨き、現場で信頼を積み重ねていけば、年収500万円以上も十分に現実的です。
収入を上げるうえで鍵になるのは、「自分をどう育てるか」と「どこで働くか」の2点です。資格の取得や職長へのステップアップはもちろん、職場選びそのものが将来の収入に影響します。働きながら成長を支えてくれる会社に出会えるかどうかは、塗装工としての人生を左右すると言っても過言ではありません。
もし、自分に合った職場環境をじっくり探したいと感じている方は、採用担当に直接質問してみるのも一つの手です。企業の考え方や育成方針を知ることで、納得のいく選択ができるはずです。
▶ ご相談やご質問がある方は、こちらからお問い合わせください