カフェや雑貨屋さんで見かける、あの味わい深い錆びた鉄の看板や家具。どこか懐かしく、温かみのあるその雰囲気に憧れて、「自分の家でも再現してみたい」と挑戦してみたものの、なんだか思ったようにならない…。そんな経験はありませんか。
ホームセンターで専用の塗料を買い、動画サイトで手順を見ながら試してみても、なぜか平面的で「いかにもペンキで塗りました」という雰囲気になってしまう。本物だけが持つ、長い時間をかけて刻まれたような重みや、複雑な色の深みが出せない。
近年、暮らしの中に個性やこだわりを取り入れるスタイルが広まり、エイジング塗装、特に「錆(さび)」の表現は多くの人から注目されています。しかし、その人気とは裏腹に、多くの人が「理想と現実のギャップ」に悩んでいるのも事実です。
それは、技術だけの問題なのでしょうか。実は、本物の質感を生み出すプロの職人と私たちの間には、単なる技術以前の、ある決定的な「視点」の違いが存在します。この記事では、その「安っぽさ」の正体を紐解きながら、多くの人が求める「本物のような深み」に迫っていきます。
そもそもエイジング塗装とは?「錆」が人々を惹きつける理由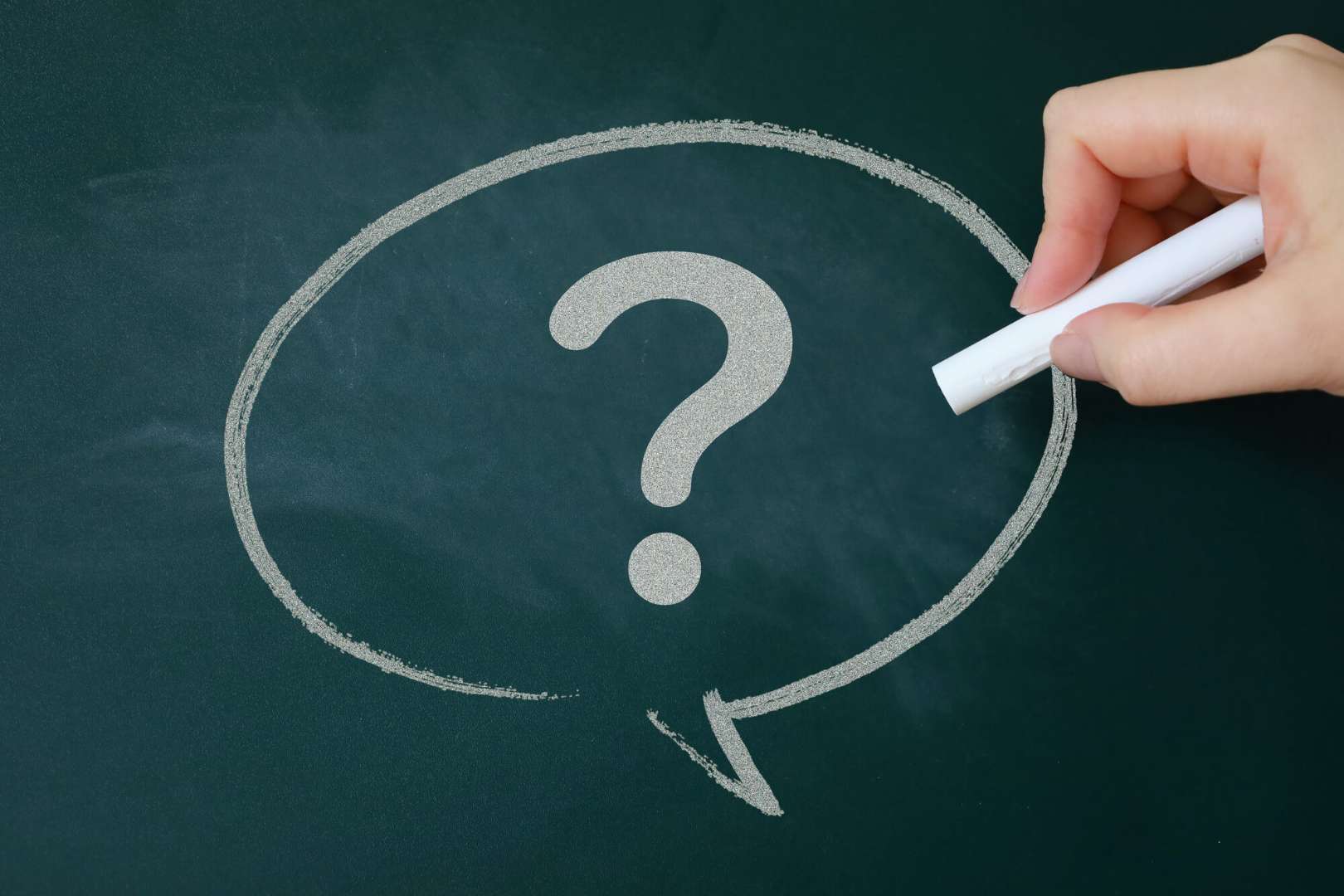
「エイジング塗装」という言葉は、少し専門的に聞こえるかもしれませんね。とても簡単に言うと、これは「新しいものに、まるで長い年月が経ったかのような見た目や雰囲気を与えるための特別な塗装技術」のことです。たとえば、真新しい木の板を、何十年も使い込まれた古材のように見せたり、ぴかぴかの金属を、雨風にさらされたヴィンテージ品のように変身させたりします。
その中でも、ひときわ人気を集めているのが「錆」の表現です。
不思議に思いませんか。本来、錆は金属が劣化していく過程で生まれるもので、どちらかといえばネガティブなイメージを持たれがちです。それなのに、なぜ私たちはデザインとしての錆に、これほどまでに心を惹きつけられるのでしょうか。
一つには、インダストリアルデザイン、つまり工場や倉庫のような、飾らない無骨なスタイルが流行していることが挙げられます。使い込まれた機械や工具が持つ、ありのままの力強さが、錆の持つ雰囲気と見事に調和するのです。
また、そこには「一つとして同じものはない」という価値もあります。自然に発生する錆の模様は、二つとありません。均一的で綺麗なものではなく、あえて不揃いで予測できないものに、私たちは人間らしい温かみや愛着を感じるのかもしれません。錆は単なる「劣化」ではなく、そのモノだけが持つ歴史や個性を語る「味」として、私たちの目に魅力的に映るのです。
「描く」のではなく「育てる」。本物の質感を左右する3つの視点

プロの職人が手がけた錆塗装と、そうでない塗装。その見た目の違いは、一体どこから生まれるのでしょうか。それは、単に高価な道具や特殊な塗料を使っているから、というだけではありません。実はプロは、錆の色を単に「描いて」いるわけではないのです。そこには、もっと根本的な、モノとの向き合い方そのものの違いがあります。
視点1:自然界の「お手本」をどれだけ知っているか
本物の錆を知らなければ、本物のような錆は作れません。プロの職人は、日頃から街中にある様々な錆をじっくりと観察しています。たとえば、雨水が常に流れる場所の錆、海の近くで潮風にさらされた錆、人がよく手で触れる部分の錆。それぞれ、色も形も、質感も全く異なります。なぜ、この場所はこんな錆び方をするのだろう?その成り立ちを深く理解しようとする「観察眼」こそが、リアルな表現の土台となるのです。
視点2:色の「層」で時間の厚みを表現する
錆と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、赤茶色かもしれません。しかし、本物の錆をよく見てみると、決して一色ではないことに気づくはずです。生まれたばかりの黒っぽい錆の上に、赤茶色の錆が重なり、さらに月日が経つと黄土色や白っぽい錆が現れることもあります。プロは、この色の「層(そう)」、いわば時間の重なりを、塗料を何度も何度も薄く重ねることで表現します。この手間を惜しまない作業が、一瞬で作ったものではない、本物の時間の厚みを生み出すのです。
視点3:そのモノが持つ「物語」を想像する力
たとえば、一枚の鉄の扉に錆塗装を施すとします。その時、職人はただ手を動かすだけではありません。「この扉は、どんな場所で使われてきたのだろう」「激しい雨風に打たれてきたのか、それとも軒下で静かに時を重ねてきたのか」。そのモノが持つ背景の「物語」を想像し、その物語にふさわしい錆を施していきます。だからこそ、出来上がったものには単なる塗装を超えた、人の心に響く深みが宿るのです。それはまるで、錆を「育てる」ような感覚に近いのかもしれません。
施工事例で解説。感動を生む「生きた錆」の作り方

頭では理解できても、実際にプロはどのようにしてあの深みを生み出しているのか、気になりますよね。ここでは、プロの仕事の裏側を、具体的な工程に沿って少しだけ覗いてみましょう。一つひとつの作業に、仕上がりを大きく左右するこだわりが隠されています。
すべては「下地」から始まる
美しい塗装は、丁寧な下準備から生まれます。これはエイジング塗装でも例外ではありません。むしろ、より重要と言えるかもしれません。ただ平滑な面に塗装するのではなく、素材の表面にあえてヤスリで細かな傷をつけたり、少し凹凸をつけたりします。この一手間が、塗料の食いつきを良くするだけでなく、後の工程で生まれる錆の表情に、より自然な陰影と立体感を与えてくれるのです。まるで、これから物語を描くための真っ白なキャンバスを、丁寧にならしていくような作業です。
道具は「刷毛」だけではない
プロの現場では、刷毛やローラーだけが道具ではありません。たとえば、塗料を含ませたスポンジで優しく叩くように色を乗せれば、じわっと広がるような錆の質感が生まれます。乾いた布で擦るように塗料を馴染ませれば、金属が擦れて剥がれたような硬質な表情を作ることもできます。時には、霧吹きで水を吹きかけ、塗料の滲みや垂れといった「偶然」の効果さえも味方につけます。決まりきったやり方はありません。表現したい錆のイメージに合わせて、最適な道具と手法を柔軟に使い分ける引き出しの多さが、表現の幅を大きく広げます。
「画竜点睛」となる最後の仕上げ
全体の錆の表情がある程度できあがったら、最後は全体のバランスを注意深く見ながら、最終的な仕上げに入ります。少し離れた場所から眺めて、物足りない部分に色を足したり、逆に強すぎる部分を馴染ませたり。雨水が垂れたような跡を細い筆で一本描き加えるだけで、驚くほど物語性が増すこともあります。この最後の「神は細部に宿る」とも言える細やかな調整が、全体の完成度をぐっと引き締め、見る人の心を動かす「生きた錆」を完成させるのです。
唯一無二の価値を創造する。エイジング塗装職人というキャリア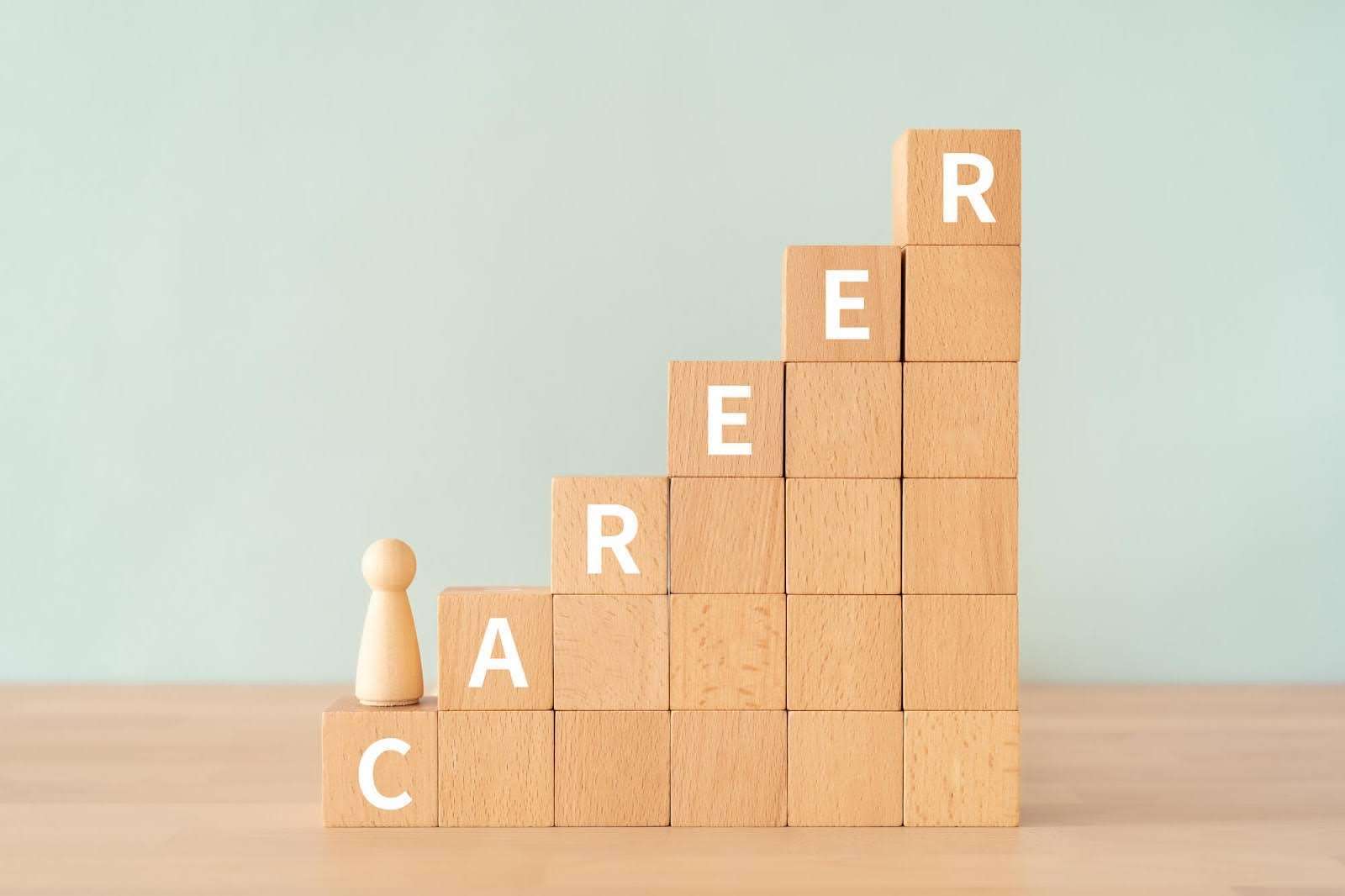
ここまで見てきたように、エイジング塗装は、決められた通りに色を塗るだけの作業ではありません。自然を観察する探究心、物語を想像する力、そしてそれを形にする繊細な技術が求められる、非常に創造性の高い仕事です。
一般的な塗装の仕事とは異なり、エイジング塗装には「正解」がありません。お客様の「こんな雰囲気にしたい」という想いを汲み取り、自分自身の感性と技術で応えていく。一つとして同じ仕上がりはなく、手掛けたものすべてが自分の「作品」となっていきます。完成したものを見て、お客様が心から喜んでくれた時の感動は、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。
そして、この専門性の高い技術は、一度身につければ、あなたのキャリアを支える強力な武器になります。「誰にでもできる仕事」ではなく、「あなたにしかできない仕事」が、ここにあります。時代の流行に左右されにくく、むしろ経験を重ねるほどに深みが増していく。そんな、自分自身の価値を高め続けられる仕事に、魅力を感じませんか。
もし、私たちの「挑戦を後押しする文化」に少しでも共感いただけたなら、私たちの価値観や働く環境について、より詳しく覗いてみませんか。
https://www.mitsuwa-painting.com/recruit
本物の価値を、その目で確かめてみませんか?
エイジング塗装によって表現された「錆」は、単に古い見た目を真似たものではありません。そこには、職人の深い観察眼、試行錯誤の末に培われた技術、そしてそのモノが重ねてきたであろう時間に寄り添う想像力が溶け込んでいます。DIYで挑戦する楽しさも、もちろん素晴らしい体験です。しかし、もしあなたが本当に心を動かされるような、本物の深みや温かみを空間に求めているのであれば、一度プロフェッショナルの仕事に触れてみる価値は、きっとあるはずです。
そして、この記事を通して、この奥深い世界の「表現する側」に興味を持った方もいらっしゃるかもしれません。自分の手で、誰かの心を動かす価値を生み出してみたい。そう感じたなら、それはあなたの新しい可能性の扉が開いた瞬間かもしれません。それは、単なる「作業員」としてではなく、感性と技術で価値を創造する「職人」としての道のりです。
この記事が、あなたの次の一歩を考えるきっかけになれば幸いです。


