「手軽にアンティークな雰囲気になる」と聞いて、スポンジを片手にDIYに挑戦してみた。雑誌で見たような、長い年月を経て深みを増した壁や家具。そんな理想の空間を思い描きながら作業を進めたものの、完成したものを前に、どこか釈然としない気持ちになっているかもしれません。
「ただペンキがムラになっただけで、汚れているようにしか見えない」
「ポンポンと叩いた跡が均一すぎて、なんだか安っぽい模様になってしまった」
「思い描いていたような、自然な古びた感じがまったく出ない」
手軽なはずのスポンジを使ったエイジング塗装は、実は非常に奥が深く、ちょっとしたコツを知らないだけで、理想とはほど遠い結果になりがちです。それは、道具の使い方以前に、本物の経年変化が持つ「質感」や「色の重なり」を表現する難しさに原因があります。
この記事では、なぜDIYのエイジング塗装が「思っていたのと違う」結果になりやすいのか、その原因と具体的な回避策を掘り下げていきます。そして、プロが創り出す本物の質感の秘密に迫ることで、あなたが本当に満足できる空間づくりのヒントを提供します。
■ スポンジだけじゃない!エイジング塗装で使える道具と基本テクニック

エイジング塗装の表現方法は、使う道具によって大きく変わります。まずは基本となるスポンジの使い方と、その他の道具がもたらす効果について理解を深めましょう。
・スポンジを使った基本的な塗装方法「タンポ塗り」
タンポ塗りとは、スポンジや布に塗料を少量つけ、ポンポンと軽く叩くようにして色を乗せていく技法です。手軽に独特のまだら模様を作れるのが最大のメリットで、コンクリートの打ちっぱなしのような質感を出すのにも使われます。
ただし、簡単そうに見えて、実は力加減や塗料の量で仕上がりが大きく左右される難しい側面も。塗料をつけすぎるとベタッとした印象になりますし、同じ力で叩き続けると不自然な模様になってしまいます。広い面積を均一な風合いで仕上げるのも、熟練が必要な作業です。
・スポンジ以外の選択肢と仕上がりの違い
理想の質感に近づけるためには、スポンジ以外の道具も有効です。
ハケ:塗料をかすれさせたり、木目のような筋を入れたりと、直線的な表現が得意です。わざと毛先の硬いハケを使うことで、ざらついた質感を出すこともできます。
布(ウエス):塗った塗料を拭き取ることで、自然な濃淡やぼかしを表現するのに適しています。角や隅の部分に溜まった塗料を拭き取ることで、使い込まれたような立体感を演出できます。
特殊なローラー:表面に凹凸のあるローラーを使えば、レンガ調や漆喰調といった特定のパターンを効率的につけることが可能です。
このように、道具を使い分けることで表現の幅は格段に広がります。
■ なぜプロの仕上がりは違う?塗料の希釈率と「重ね塗り」の奥深い世界
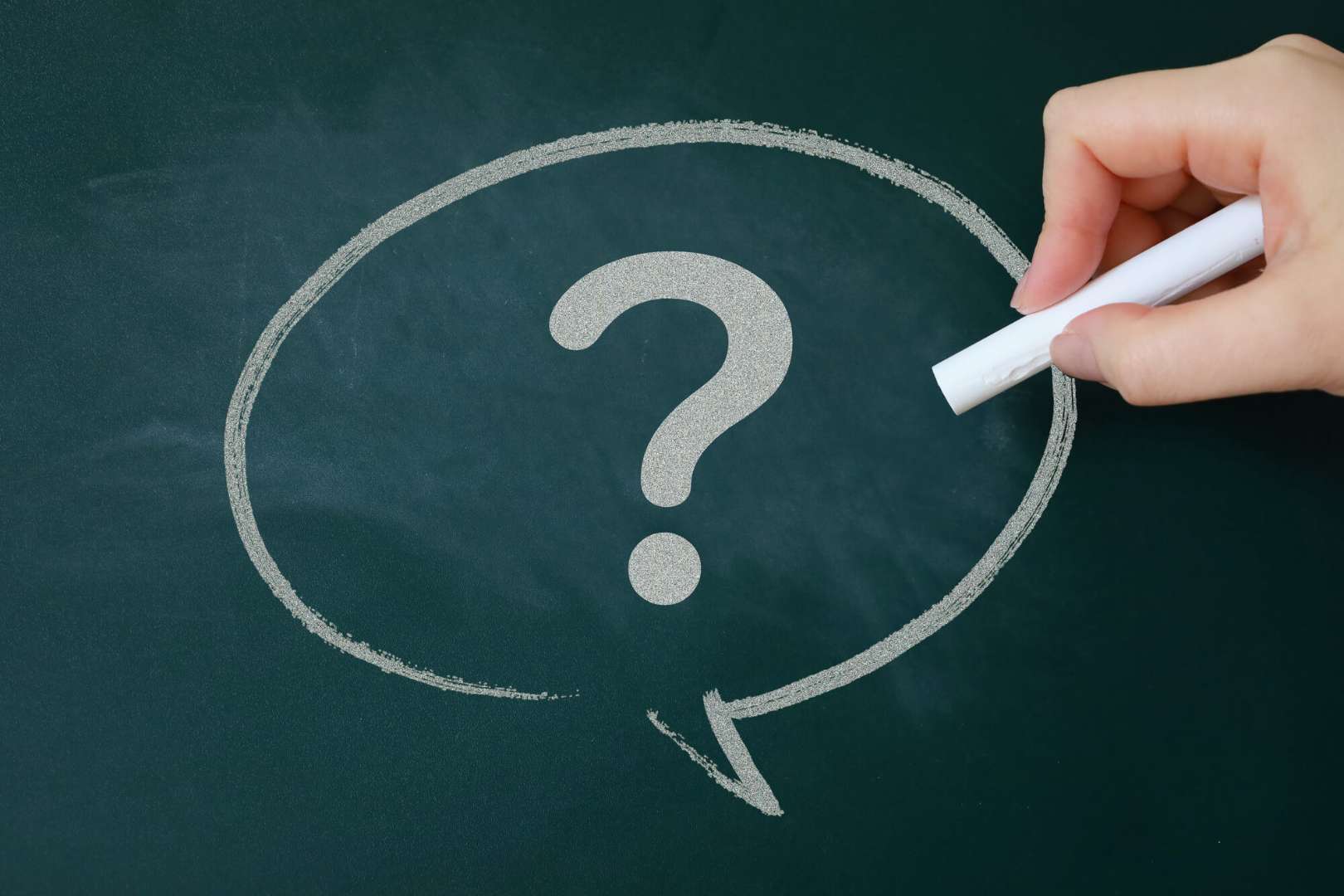
プロのエイジング塗装が本物のように見える理由は、単に道具の使い方が上手いからだけではありません。その秘密は、塗料そのものの扱いや、色の重ね方といった、目に見えにくい部分に隠されています。
・仕上がりの9割を決める「塗料の希釈率」
専門家が最も神経を使う工程の一つが、塗料の希釈、つまり薄め具合の調整です。塗料が濃すぎれば、のっぺりとした「ペンキを塗りました」という印象が強くなります。逆に薄すぎると、色が乗らずに下の素材が透けすぎてしまいます。プロは、その日の気温や湿度、塗装する素材の状態を考慮しながら、コンマ数パーセントの単位で希釈率を微調整します。この絶妙な調整が、わざとらしくない自然な風合いを生み出すのです。
・深みを創り出す「色のレイヤリング(重ね塗り)」技術
エイジング塗装の核心ともいえるのが、複数の色を何層にも重ねる「レイヤリング」という技術です。例えば、壁を古びたように見せる場合、ただグレーの塗料を塗るわけではありません。まずベースとなる色を塗り、その上に少し濃い色を乗せてから部分的に拭き取ることで影を作り、さらにごく薄い白をかすれさせてハイライトを入れる、といった具合です。このように、何層もの色が重なり合うことで、単色では決して表現できない、本物の経年変化だけが持つ色の深みと奥行きが生まれます。
・経験がものをいう「独自の調色データ」
創業50年を超えるような経験豊富な塗装業者には、長年の経験から蓄積された膨大な調色データが存在します。それは、ただ色見本を見て色を混ぜるのではなく、「〇〇年代のフランスの古城の壁」「雨風にさらされた鉄の錆」といった具体的なイメージを、塗料の配合で再現するための設計図のようなものです。こうした専門知識と経験の積み重ねこそが、DIYでは決して到達できない、プロの仕上がりを支えています。
■ 初心者が陥る3つの罠|「ベタ塗り感」「不自然な模様」「養生の甘さ」
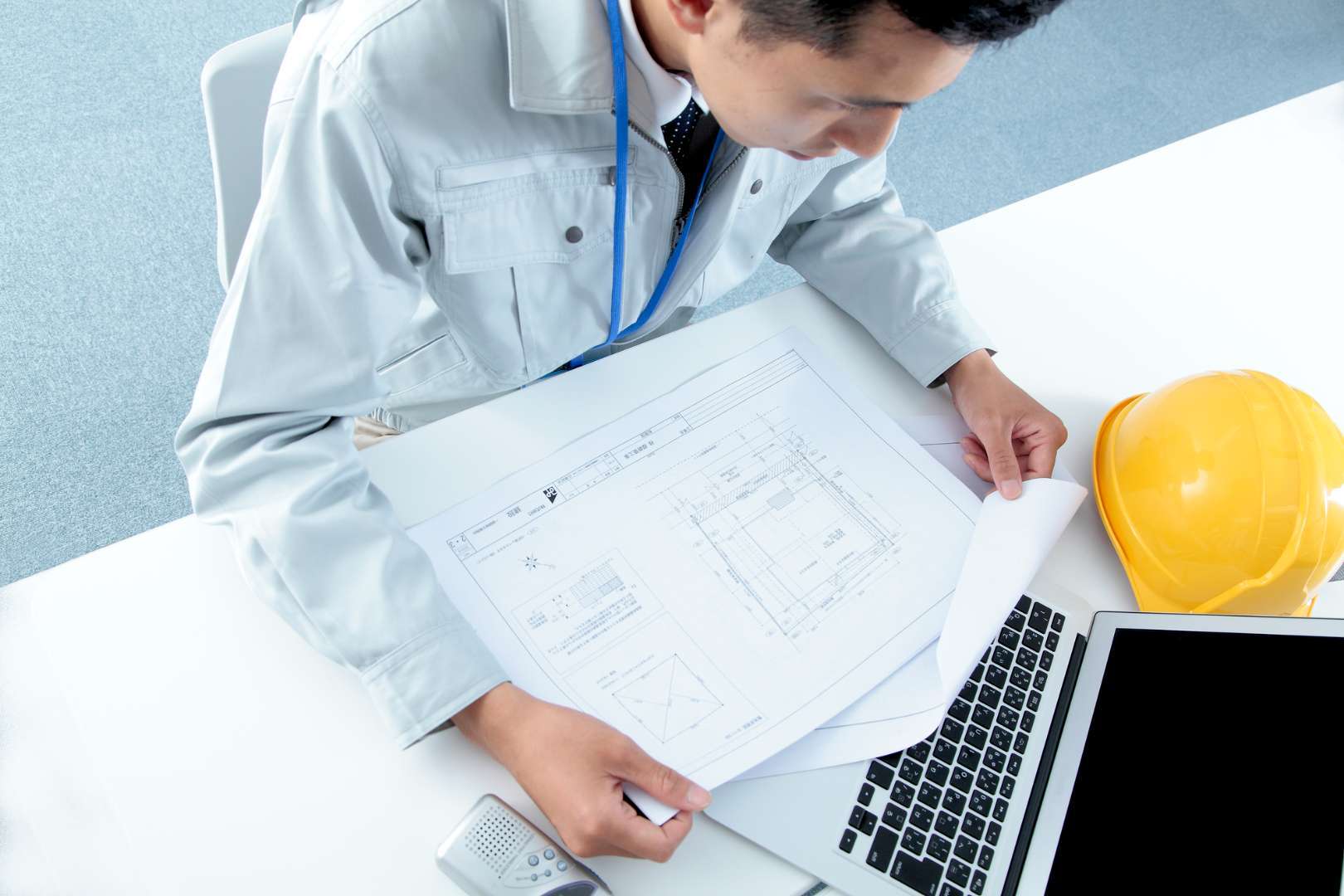
DIYでのエイジング塗装には、知らず知らずのうちに陥ってしまう典型的な失敗パターンがあります。ここでは特に多い3つの罠と、それを回避するための具体的な対策を見ていきましょう。
・罠①:「ベタ塗り感」が出てしまう
これは、スポンジに塗料を含ませすぎることで起こる最も多い失敗です。良かれと思ってたっぷりと塗料をつけると、叩いた部分がベタッとした塊になり、繊細な濃淡が表現できません。
【回避策】
塗料をパレットなどに出し、スポンジに少量だけつけるのが基本です。さらに、いきなり壁に叩きつけるのではなく、必ず不要な紙や板の上で数回ポンポンと叩き、余分な塗料を落としてから作業を始めましょう。「少し色が薄いかな?」と感じるくらいが、重ね塗りをしながら調整していく上で最適です。
・罠②:同じ繰り返しによる「不自然な模様」
無意識のうちに同じ力加減、同じ角度でスポンジを叩き続けると、スタンプを押したような人工的な模様になってしまいます。自然な経年変化は、もっとランダムで不規則なものです。
【回避策】
スポンジを持つ手首の角度を毎回少しずつ変えたり、叩く力の強弱に変化をつけたりすることを意識してください。時にはスポンジの角を使ったり、面で広く押さえたりと、動きにバリエーションを持たせることが、自然なムラを生み出すコツです。
・罠③:「養生の甘さ」による周囲への汚れ
エイジング塗装は、意外と塗料が飛び散りやすい作業です。床や周りの家具、窓枠などの養生(マスキング)が不十分だと、完成後に余計な清掃の手間が増えたり、最悪の場合、汚したくない部分にシミが残ってしまったりします。
【回避策】
「このくらい大丈夫だろう」と楽観視せず、塗装する箇所の周辺はマスキングテープやマスカー(テープとビニールシートが一体化したもの)で広めに覆いましょう。特に、天井や壁の上部を塗装する際は、塗料が垂れてくることも想定して、床の養生は完璧に行うことが後悔しないための重要なポイントです。
■ 「本物の質感」を求めるなら。後悔しない塗装業者の選び方

DIYには手軽さという魅力がありますが、時間や手間をかけた結果、満足のいく仕上がりにならなければ、その労力は報われません。もしあなたが、雑誌で見るような「本物の質感」や、空間全体の雰囲気を変えるほどのクオリティを求めるなら、専門家への依頼が最も確実な選択肢となります。
では、何を基準に業者を選べば良いのでしょうか。後悔しないための3つのポイントを紹介します。
長年の実績と豊富な施工事例があるか
エイジング塗装のような特殊な技術は、一朝一夕で身につくものではありません。その業者がどれだけの経験を積んできたかは、信頼性を測る重要な指標です。例えば、創業から50年以上続いているような会社であれば、それだけで多くの現場を経験し、技術を磨き続けてきた証と言えるでしょう。公式ウェブサイトなどで、具体的な施工事例の写真を数多く確認できるかどうかも必ずチェックしましょう。
特殊塗装に関する専門知識と技術力があるか
ただペンキを塗るだけの業者と、エイジング塗装を専門的に手掛ける業者とでは、知識も技術も全く異なります。塗料の種類や特性、素材との相性、そして何より美的センスが問われます。相談の際に、こちらの曖昧なイメージを汲み取り、専門的な視点から具体的な仕上げの提案をしてくれるかどうかが、技術力を見極めるポイントです。
要望を丁寧にヒアリングし、完成イメージを共有してくれるか
特に重要なのが、コミュニケーションの質です。優れた業者は、一方的に施工を進めることはありません。打ち合わせから施工、完成までを一貫して自社の職人が担当する体制が整っている会社は、要望の食い違いが起こりにくく、細かなニュアンスまで汲み取ってくれる傾向があります。あなたの「こうしたい」という想いを丁寧にヒアリングし、完成までのプロセスを共有してくれる業者を選びましょう。
さらに、壁一面だけでなく、ドアや建具、家具まで含めた空間全体で統一感のあるデザインを提案できる業者であれば、より完成度の高い空間を実現できます。こうしたトータルでの提案力も、業者選びの際に注目したい点です。
有限会社ミツワの事業内容について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
■ 理想の空間を、失敗という遠回りをせずに手に入れるために
ここまで、スポンジを使ったエイジング塗装のコツと、DIYで陥りがちな失敗、そしてプロの技術について解説してきました。
スポンジを使ったDIYは、手軽に始められる一方で、安っぽく見えてしまうリスクと隣り合わせです。一方、プロの仕事は、単に道具を使いこなすだけでなく、塗料の知識、色の重ね方、そして長年の経験に裏打ちされた美的センスといった、目には見えない要素の結晶です。
もしあなたが今、DIYに挑戦するか、プロに頼むかで迷っているのなら、まずは専門家が手掛けた「本物のエイジング塗装」がどのようなものか、じっくりと見てみることから始めてはいかがでしょうか。その圧倒的な質感と深みを知ることで、あなたの理想の空間がより明確になるはずです。
遠回りをして後悔する前に、一度専門家の話を聞いてみる。それも、理想の空間づくりに向けた賢明な一歩です。


